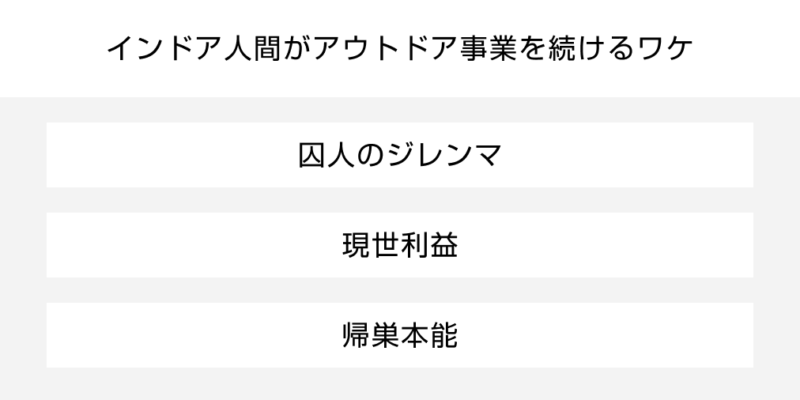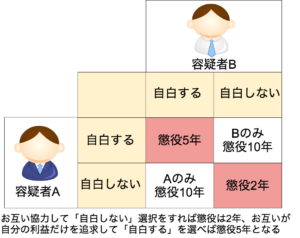おうち時間が増えている。
みなさん、おうちで何してますか?
僕は人との会話が週一のMTGだけになりました。あとは家族と適宜電話。
そんな状況なので、寂しさを紛らわせるためにラジオを聞く人が増えているとかいないとか。
個人的にここ3、4年は音声コンテンツにハマっていてせっかくなので日頃聞いているものをまとめます。
もし気になるものがあれば、おうち時間のお供にどうぞ。
Podcast編
一宿一飯
20代の4人組が、毎回「普通」の人をゲストに招いてお話を聞くポッドキャスト。ゲストはもしかしたら、昨日電車であなたの隣に座った人かもしれません。
ニーナの今週も仕入れてきましたよ
ベンチャーキャピタルANRIの江原ニーナさんが、スタートアップの主に調達ニュースを仕入れてくる番組。もしかしたらstand.fmに移行したかもしれない。
rehash.fm
IT界隈のニュースや話題、そしてアニメについてお話ししている番組。
LOGOS presents CAMP RADIO
MEGUMIさんが毎回ゲストを招いてキャンプやアウトドアの楽しい“外遊び”を伺っていくトーク番組。
ノウカノタネ
「農業の世界を知れば人生の”食べる””働く“がもっと奥深くなる」 社会の最底辺から根幹を支える若手農家の雑談を垂れ流す、井戸端ポッドキャスト 。らしいです。
Rebuild
説明不要。最も古くからある?著名エンジニアの方々の番組。IT界隈ポッドキャスターの目指す場所。
mercan.fm
メルカリ社内の音声版オウンドメディア的な番組。
フィッシングトレイン
釣具販売のキャスティング社による釣り情報番組。僕は釣りをやらないので、話していることの95%理解できないですがなんとなく聞いている。
伊藤洋一のRound Up World Now!
経済番組です。週一で情報拾うために聞いている。
TENGA presents Midnight World Cafe ~TENGA 茶屋~
TENGAの番組です。以上!
主に日本の歴史のことを話すラジオ
ただの歴史好きなパーソナリティ2人が歴史をテーマにあれこれと雑談をするポッドキャスト番組。
Modern Syntax Radio Show
主にIT業界の方をゲストに迎えてお話ししている番組。
engineer meeting podcast
ITエンジニア3人によるあれやこれやの雑談番組。
backspace.fm
一週間分のテック・ガジェットニュースを配信するポッドキャスト。1エピソード平均で2時間以上あるので非常に長いです。
Takram Cast
東京・ロンドン・ニューヨークを拠点に様々なプロジェクトに取り組むデザイン・イノベーション・ファームであるTakram社による雑談、考察番組。発見が多いのでオススメです。個人的には、議論の引用元となっていたり、紹介されている本を買うことが多い。
TAKRAM RADIO PODCAST
同じくTakram社の渡邉康太郎さんによるラジオ番組の、完全収録版。ラジオの方も聞いている。
Automagic Podcast
Webやアプリのデザインの仕事に携わる長谷川恭久さんが、今活躍していらっしゃるプロの方を招いていろいろな話をしている番組。
The Potluck Cast
アメリカ・サンフランシスコやニューヨーク、時々東京の気になるプロダクトや企業、ブランドについて異なる角度から読み解いている番組。
白と水色のカーネーション
日々日常の出来事の記憶、雑談のお話し。
こんにちは未来 〜テックはいいから
音楽、アート、政治、ビジネス、ライフスタイル、メディアまでカテゴリーにとらわれず縦横無尽に語りつくすトークセッション。
ゼロトピック – Zero Topic
みんな大好きYamottyさんの独り言番組。勉強になります。
ゆとりっ娘たちのたわごと
知る人ぞ知るゆるふわ番組。
Off Topic // オフトピック
米国を中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるーく深堀りしながらご紹介する番組。
未来授業
「FMフェスティバル 未来授業~明日の日本人たちへ」のレギュラー番組。
ドングリFM
みんな大好き、なつめぐさんとなるみさんの番組。基本的に面白い&ためになるよ。
飯田浩司のOK! Cozy up!
朝のニュース情報番組。基本的にニュースはこれで確認してます。
こちカブ~こちらaukabucom投資情報室
前日の海外市場の情報や解説から、その日の東京市場のポイントなどを話す朝の株式投資情報番組。基本的に経済情報はこれで確認してます。
FASHIONSNAP.COM ポッドキャスト
FASHIONSNAP.COM がお届けする注目のファッションニュースやトレンド情報を話す番組。なんとなく聞いている。
その他:更新が停止していたり、ほぼ更新していない番組など
ホシハヤトとヒルティのインターネット汁
ひいきびいき
スタートアップ
ヤバイホームページ屋さんのPodcast
Podpatch
だんごゆっけの平和な話
にゃにゃにゃラジオ…etc
Radiotalk編
ピーチフルの駅徒歩20分ラジオ
都内在住OLのピーチフルが仕事終わりの駅徒歩20分、歩きながら喋りる番組。
サイコーの飲み会がしたい
こじらせ女子大生が飲み会で話したいようなことを好き勝手話してるラジオ。
FREE AGENDA
メルカリでグロースを務めてきたヒカルさんと株式会社10Xの創業者&代表であるYamottyさんがビジネスやテクノロジー、スタートアップなどをトピックに話す番組。
YouTubeに移行したっぽい。
と思ったらnoteにも移設してました。
ラジオ(radiko)編
INNOVATION WORLD
ラジオから東京、そして日本をイノベーション!テクノロジーの進化を追うラジオプログラム。
INNOVATION WORLD ERA
真鍋大度、後藤正文 (ASIAN KUNG-FU GENERATION)、のん、小橋賢児の 4 人のクリエイターが週替わりでナビゲートして各界のイノベーターをお迎えしてイノベーションの種をお届けする番組。
村上信五くんと経済クン
「経済初心者」の村上信五さんが、ゲストの方に教えを請いながら「お金」に強くなってゆく番組。らしい。
TAKRAM RADIO
デザインファームTakramの渡邉康太郎さんが、いま注目するひと、場所、アートや音楽をピックアップ。未来を切り開くインスピレーションをお伝えする番組。
SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記
草野さんが、古今東西イケてるロックナンバーを紹介していく番組。
菅田将暉のオールナイトニッポン
ただただ面白い。いま一番放送を楽しみにしている番組かもしれない。
しかし今週からリモート収録になり、作家さんとの意思疎通が難しそうで面白さ半減しておりもったいない…
VOICES FROM NIHONMONO
中田英寿さんが日本各地で出会った文化、伝統、食の数々。その土地でしか出会えない「にほんもの」の声をとどける番組。なにげに好きです。
SHOWROOM主義
SHOWROOM前田さんがあれこれ喋る番組。
マスメディアン 妄想の泉
ハヤカワ五味さんが起業家やクリエイター、アーティストなど迎えてあれこれ喋る番組。
問わず語りの神田伯山
講談師神田松之丞改め、神田伯山のぼやきラジオ。何も考えずに聞けます。
番外編
SCHOOL OF LOCK!
10代に異常な人気を誇るモンスター番組。懐かしい…
10年間校長を務めたとーやま校長はこの3月で引退したようです。
以上、あれやこれやの音声コンテンツ紹介。ほとんど公式の紹介文を引用してます。
家事してたり移動中だったり散歩中に聞くことが多い。
Stay Homeで寂しくなったら
声をきこうぜ